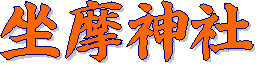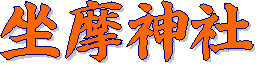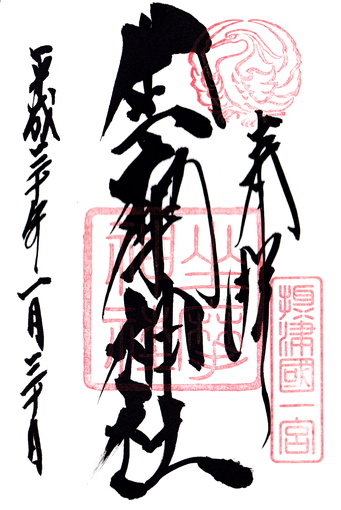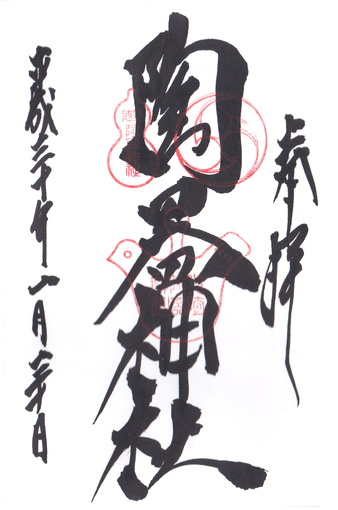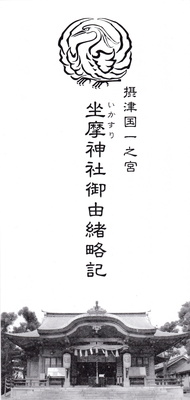|
府 県 |
大阪 |
|
朱印番号 |
G32/G33 |
| 寺
社 名 |
坐摩(いかすり)神社/火防陶器神社 |
|
別称
etc |
ざまじんじゃ |
|
所
在
地 |
大阪市中央区久太郎町四丁目渡辺3号 |
| 山
号 |
|
|
参
拝
日 |
H30.01.30 |
| 宗
派 |
|
|
主な札所 |
神仏霊場巡拝の道49番(大阪8番) |
| |
|
| |
|
| 主 祭
神 |
坐摩神 |
|
特記事項 |
地下鉄の本町駅から南へ350mの所にありま
す。坐摩神社の創祀には諸説がありますが、
神功皇后が新羅より御帰還の折、淀川南岸の
大江、田蓑島のちの渡辺の地(現在の天満橋
の西方、石町附近)に奉祀されたのが始まり
とされています。平安時代の「延喜式」には
攝津國西成郡の唯一の大社と記され、産土神
として今日に至っています。また939年以
来祈雨11社中に列し、以後たびたび祈雨〔雨
乞い〕のご祈請・奉幣に預かりました。
火防陶器神社は明治6年の創建ですが、その
起源は明暦年間(1655~1657)にさかのぼり
ます。信濃町(現在の西区靭本町1丁目付近)
の石灰商・山田喜六の邸内に火災の難を除か
せ給う愛宕山将軍地蔵が祀られ、空地に小屋
を設けて祀ったところ、多くの参詣者が訪れ
たといいます。延宝年間(1673~1681)には
近隣の西横堀に陶器商が軒を並べ瀬戸物町が
形成され、火防のご利益著しいことから特に
陶器商の信仰を集めました。その後、西横堀
川に高速道路が建設されるなど数々の変遷を
経て、この地、坐摩神社の境内に移りました。
|
|
|
|